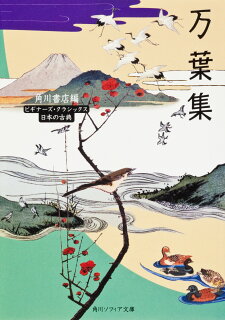遣唐使として中国大陸に渡り、現地で重用されました。
任期が終わり、帰国の途についた時に詠んだ歌が百人一首に収められています。
ただ、残念ながら阿倍仲麻呂は帰国できなかったようです。
今回は阿倍仲麻呂(仲麿)について紹介します。
阿倍仲麻呂(仲麿)とは
阿倍仲麻呂は奈良時代の人。生年は698年とされています。没年は770年。
遣唐使として中国に渡ったのが717年なので、19歳で留学したことになります。
現地で科挙(唐の役人としての登用試験)に合格するほどの秀才でした。
753年に帰国の途につきますが、船が難破して漂流することになります。
はるか南方に流されますが、755年に長安(唐の都)にたどり着きます。
その後は帰国をあきらめ、現地での役人として生涯を過ごすことになりました。
時代背景
当時の唐は玄宗皇帝のころ。
またソグド人の安禄山も重用されていて、北方の地の節度使となっていた。
安禄山が、宰相で楊貴妃の従兄弟である楊国忠と対立、挙兵したのが755年。
これが安史の乱と呼ばれる騒乱の始まりでした。
唐の国は安史の乱の後、衰退を続け、周辺諸国からの侵入を受けるようになります。
大国の末期の様子を、阿倍仲麻呂は近くで見ながら、どのようなことを考えたでしょうか。
百人一首の歌
歌 天の原ふりさけ見れば春日なる三笠の山に出でし月かも
歌の意味:ふり仰いで見れば月が出ている。この月は故国の春日にある三笠の山に出ていたあの月と同じなのだ。
阿倍仲麻呂(仲麿) 唐の衰亡を見続けた才人
当時の日本は大陸中国の動向を無視しては国の運営ができませんでした。
そのような状況の中、遣隋使、遣唐使として多くの秀才が中国に渡り、知識や文化を持ち帰りました。
ただ、当時は海を渡るのは命がけ。
途中で難破することもしばしばでした。
阿倍仲麻呂をはじめ、何人もの人が帰国できなかったことでしょう。
またお立ち寄り下さい。
ひき続きどうぞご贔屓に。
| 万葉集 ビギナ-ズ・クラシックス /角川学芸出版/角川書店 | ||||
|

にほんブログ村ランキングに参加しています