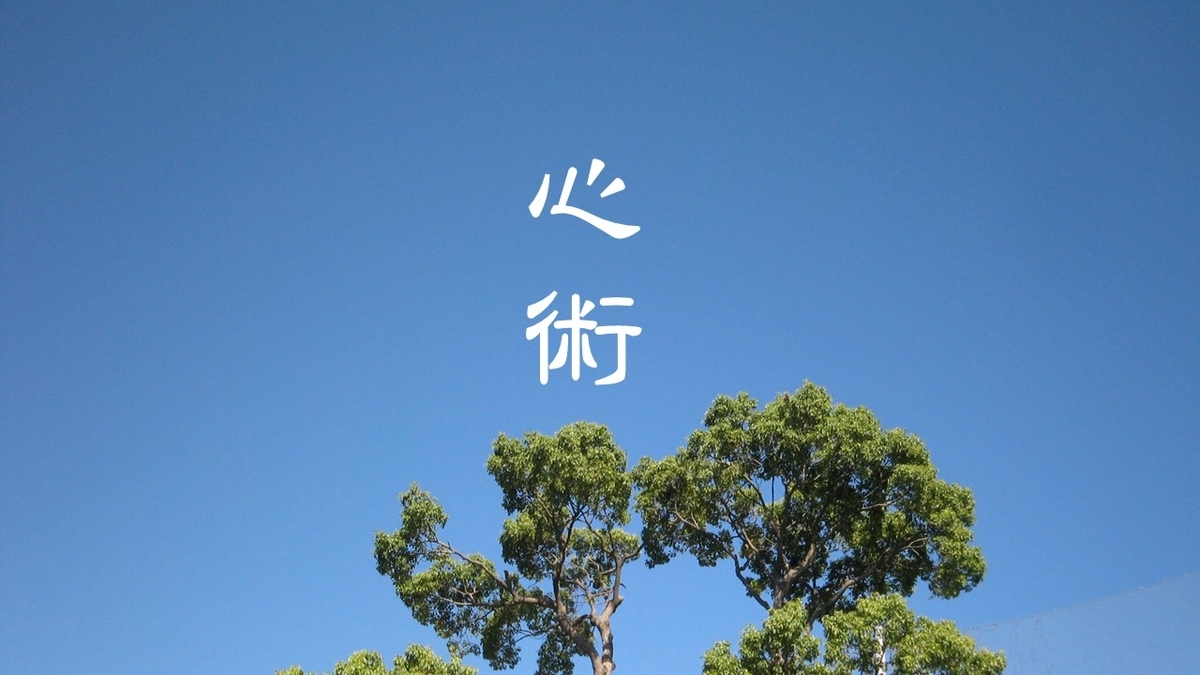
こんにちは、暖淡堂です。
心術上の第六回目です。
道の在り方を、その大きさで説明している文章を紹介します。
その文章を参考にしながら、道について考えてみたいと思います。
心術上第三十六(短語十)
原文
道在天地之閒也、其大無外、其小無内。故曰、不遠、而難極也。
書き下し文
道の天地の閒にあるや、その大なること外無く、その小なること内無し。故に曰く、遠からずして、しかも極め難きなり、と。
現代語訳
道は天と地との間にあり、それは外から包むことができるものが無いくらい巨大であり、それよりも内側に入りこめるものがないくらい微小である。なので、道は遠いどこかにあるのではないが、しかし極めるのがとても難しいといわれるのだ。
「菅子四篇」暖淡堂書房より
<簡単な解説>
閒の字、面白いですね。間の日が月になっています。どうも順番的には閒の方が古いようです。
金文では門の上に肉を書くものもあります。祖先を祀る儀礼に関係して書かれた文字のようです。
今回の文章では間、あいだの意味で読みたいと思います。
道は天と地との間にありますが、それはとても大きく、その外はないほどです。
何よりも大きい。
天も地も、道の中にあるのです。
で、道はまた、それよりもさらに内側にあるものはないほどに小さなところにまである。
つまりは、天と地との間にあるものをすっぽりと覆い、またその一番小さな隙間さえも入り込んでしまっている。
天と地とは、道の中に浸かっているかのような状態ですね。
もう、どっちに向かっていっても、私たちは道の中にいるのです。
菅子四篇 心術上 (6)
道在天地之閒也、其大無外、其小無内。
道の在り方について、その大きさでの説明
国内で販売されている「管子」はいずれも高価です。
また抄訳本では残念ながら「菅子四篇」部分は含まれていません。
なぜか、「管子」の主要部分とは見なされていないからのようです。
暖淡堂書房「菅子四篇」は、その部分にむしろ焦点を当てて作成しました。
現在Kindleの電子書籍として持ち運びに便利な形で販売中。
アマゾンのペーパーバックとしても入手可能です。
東洋思想の源流を概観するのにも効果的な書物になっています。
仏教が中国に受容され、その後禅として発展したことの背景も理解できるかもしれません。
ぜひご一読を。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。

にほんブログ村ランキングに参加しています



