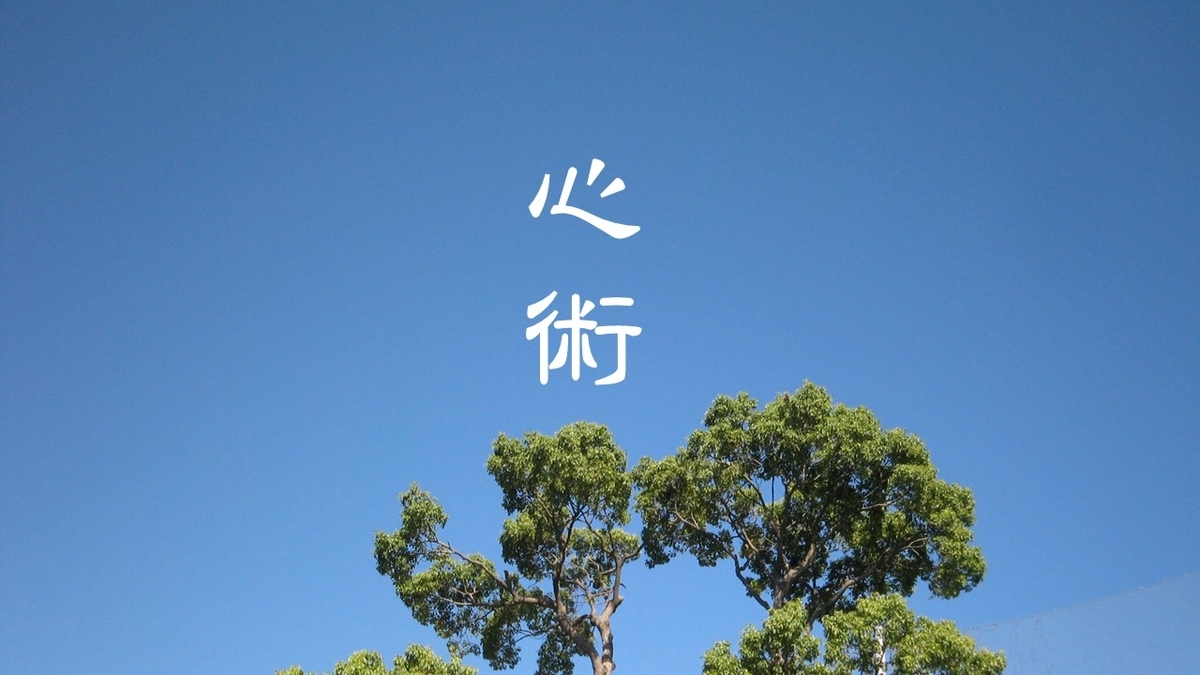
こんにちは、暖淡堂です。
心術上の第五回目です。
心術上の冒頭部分の内容が、改めて説明されています。
ここではそれぞれの職分をきちんとわきまえている状況ができたうえで、君主が取るべき態度を述べています。
心術上第三十六(短語十)
原文
心之在體、君之位也。九竅之有職、官之分也。耳目者視聽之官也。心而無與於視聽之事、則官得守其分矣。夫心有欲者、物過、而目不見、聲至、而耳不聞也。故曰、上離其道、下失其事。故曰心術者、無爲而制竅者也。故曰、君、無代馬走、無代鳥飛。此言不奪能、能不與下誠也。毋先物動者、揺者不定、躁者不靜、言動之不可以觀也。位者謂其所立也。人主者立於陰。陰者靜。故曰、動則失位。陰則能制陽矣。靜則能制動矣。故曰、靜乃自得。
書き下し文
心の體にあるは、君の位なり。九竅の職あるは、官の分なり。耳目は視聽の官なり。心、視聽のことに与ることなければ、すなわち官はその分を得る。それ心に欲あるものは、物過ぎるも、目見ず、聲至れども、耳聞かざるなり。故に曰く、上その道を離れれば、下その事を失うと。故に曰く、心術なるものは、無爲にして竅を制するものなりと。故に曰く、君は馬に代りて走ることなく、鳥に代りて飛ぶことなしと。これ能を奪わずしてよく下誠なるに與(あずか)らざるをいう。物に先だちて動くなかれとは、揺れるものは定まらず、躁なるものは静ならず、動の以て観るべからざるをいう。位なるものはその立つところをいう。人に主たるものは陰に立つ。陰は静なり。故に曰く、動けばすなわち位を失うと。陰なればすなわち能く陽を制す。静なればすなわちよく動を制す。故に曰く、静なればすなわち自ら得、と。
現代語訳
心は身体の中にあり、身体を治める役割を担っている。それは君主のようなものだ。身体にある九つの穴にはそれぞれの役割があり、異なった働き方をする。耳目は見聞きする器官である。それらは君主に仕える官吏のようなものだ。本来、身体を治めるべき心が、これら耳目の役割に与らなければ、それぞれの器官はその役目をきちんと果たすことができる。心に余計な欲を持っていると、物が目の前を過ぎても目はそれを見ることができず、音が鳴っても耳は聞き取ることができない。だから、もし治める立場のものがそのあり方を離れてしまえば、従うものはその役割を見失ってしまうのだ。このように、いらざることをなさずにして、治めることを心術という。それで、君は、馬に代って走らず、鳥に代って飛ぶこともしないといわれるのだ。これは力あるものの能力を奪うことなく、物事に誠実に取り組ませて口出ししないことをいうのだ。物事に先立って動くなというのは、動揺するものは安定せず、走り回るものは落ち着かず、自ら動いたのでは物事の法則を観てとることができないためだ。位とは、治める立場の者が立つべき所をいう。人に主となる者は表立っては立たず、陰にいるものだ。陰にいるとは、静かに動かないでいることをいう。だからいうのだ、動けば、あるべき場所から離れてしまう。陰にいれば、表にあるものをうまく制することができ、静かに止まっていれば、動いているものを制することができる。静かに止まっているとは、自らのあるべき位置を保っていることである。
「菅子四篇」暖淡堂書房より
<簡単な解説>
国をまとめるために働く官吏が、自分の職分をわきまえ、それぞれに力を尽くすようにすることが第一歩。
それが実現されると同時に、君主は表に立たず、欲に動かされて余計なことをせず、あるべき位置に静かに止まっている。
それが国が穏やかに収まり、民が幸せに暮らしていくためのあり方だと説明しています。
このような君主のあり方を実現するのが「心術」だとも言っています。
「心術」の要諦を簡単に述べていますね。
菅子四篇 心術上 (5) 靜乃自得。
自らのあるべき位置を保つ
国内で販売されている「管子」はいずれも高価です。
また抄訳本では残念ながら「菅子四篇」部分は含まれていません。
暖淡堂書房「菅子四篇」はKindleの電子書籍として持ち運びに便利な形で販売中。
アマゾンのペーパーバックとしても入手可能です。
東洋思想の源流を概観するのにも効果的な書物になっています。
仏教が中国に受容され、その後禅として発展したことの背景も理解できるかもしれません。
ぜひご一読を。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。

にほんブログ村ランキングに参加しています



