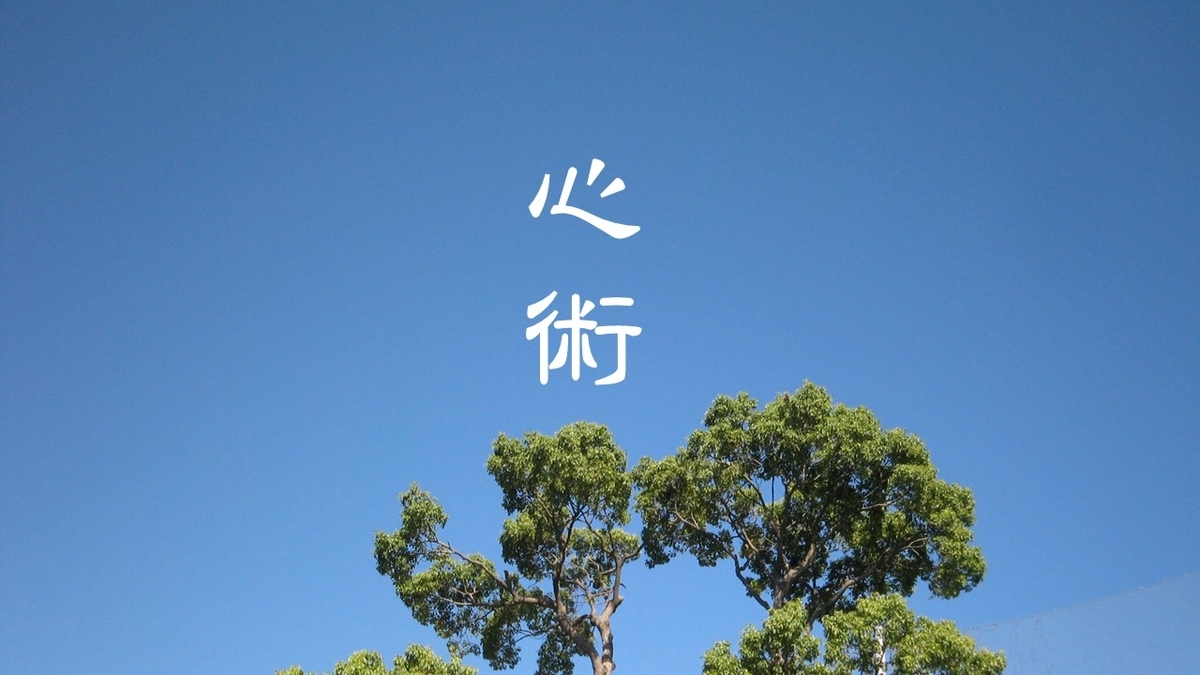
こんにちは、暖淡堂です。
心術上の第四回目です。
これまでは「道」について説明してきました。
今回は「道」とともに生きる「君子」についての文章です。
「君子」は、ときに「聖人」と呼ばれることもあります。
心術上第三十六(短語十)
原文
人之可殺、以其惡死也。其可不利、以其好利也。是以、君子不休乎好、不迫乎惡、恬愉無爲、去智與故。其應也、非所設也、其動也、非所取也。過在自用、罪在變化。是故、有道之君、其處也、若無知、其應物也、若偶之、靜因之道也。
書き下し文
人のこれを殺すべきは、死を惡(にく)むを以てなり。それ利せざるべきは、利を好むを以てなり。これを以て、君子は好みに休んぜず、惡に迫られず、恬愉無爲にして、智と故とを去る。その應ずるや、設くるところにあらず、その動くや、取るところにあらず。過ちは自用するにあり、罪は變化にあり。この故に、有道の君は、その處るや、知無きがごとく、その物に應ずるや、これに偶するがごときは、靜因の道なり。
現代語訳
人を殺すことが罰になるのは、人は死を嫌がるからである。利を与えないことが戒めになるのは、人は利を好むものだからである。だから、君子は、好むものだけを頼ることもなく、憎む感情に動かされることもない。ゆったりとした暮らしを喜び、知識も道理も、ともに捨て去っているのだ。物事に対応するときは、予め設けていた仕方にこだわることなく、動くときも、自ら求めて動くことはない。過ちは道のあり方からはずれて、自分の考えで物事をなすところにあり、罪は道のあり方にかなった自分を変えてしまうところにある。だから、道とともにある君子は、知恵で動いているのではないかのようであり、それでいて、世の中の出来事には、丁度適うような対応をするのであり、静かに道の理にしたがうだけである。
「菅子四篇」暖淡堂書房より
<簡単な解説>
「道」とともに生きる人が「君子」です。
「道」は、私たちのすぐそばにあり、寄り添うようにしているのですが、それに私たちは気づいていません。
心の中を余計なものでいっぱいにして、周囲で起こるものごとに振り回されて毎日を生きています。
「君子」や「聖人」は、心の中に溜まりがちな余計なものを放り出し、空にしたところに「道」を呼び込みます。
そして自然に「道」が実現するものと一体となって生きていきます。
そのように生きていると、あれがいい、これが悪い、あれが好きだ、これが嫌いだ、などということを考えなくなります。
世の中とは、人間が余計なことをしなければ、「道」がそのまま実現されていくもの。
人間があれやこれや、ことさらなことをして、それで混乱させています。
本来の静かなあり方をしていれば、世の中は治っていくもの。
今回紹介したのは、そんなことを言っている文章になります。
菅子四篇 心術上 (4) 君子不休乎好。
好むものだけに頼らない
国内で販売されている「管子」はいずれも高価です。
また抄訳本では残念ながら「菅子四篇」部分は含まれていません。
暖淡堂書房「菅子四篇」はKindleの電子書籍として持ち運びに便利な形で販売中。
アマゾンのペーパーバックとしても入手可能です。
東洋思想の源流を概観するのにも効果的な書物になっています。
仏教が中国に受容され、その後禅として発展したことの背景も理解できるかもしれません。
ぜひご一読を。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。

にほんブログ村ランキングに参加しています



