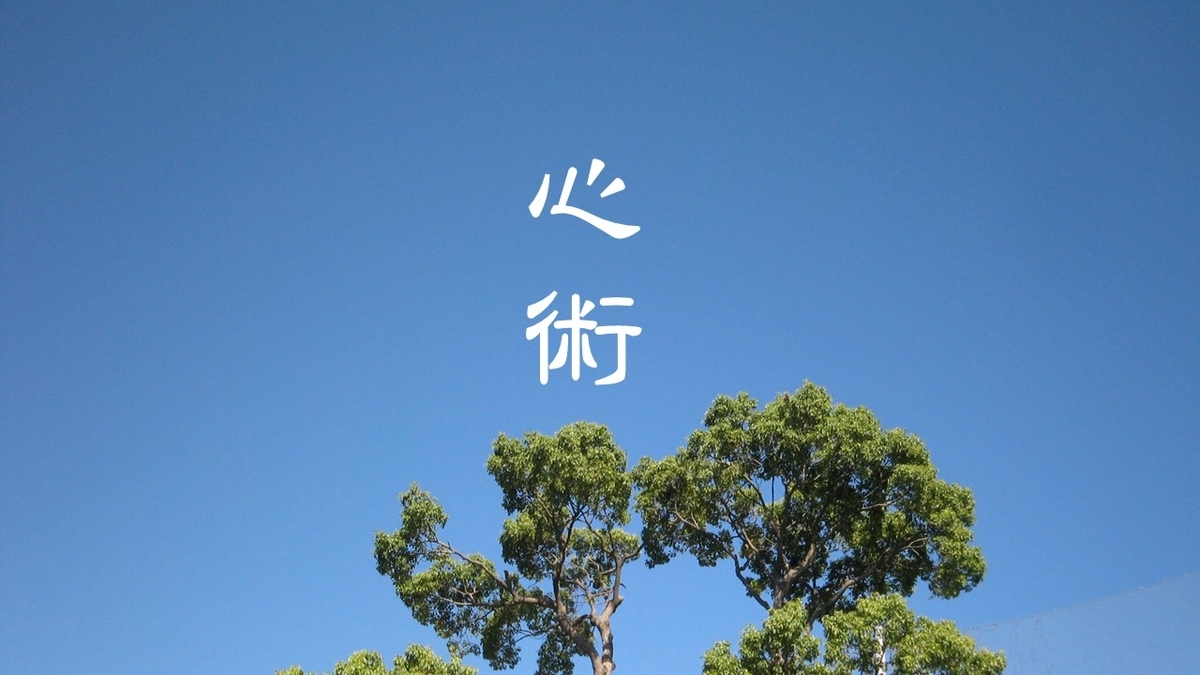
こんにちは、暖淡堂です。
少し間があいてしまいましたが、「菅子四篇」の紹介を再開したいと思います。
管仲は、中国春秋時代、当時の中国北東部にあった斉という国の宰相を務めた人物。
彼は国の制度を改め、経済を発展させ、その結果としての強い国を実現しました。
その管仲の名のもとに集められた文章をまとめたのが「管子」という書物です。
管仲自身の文章を中心に、その後斉で活躍した思想家の文章も合わせて、膨大な文字数の書物になっています。
「菅子四篇」はその「管子」の中の「心術上、心術下、白心、内業」の四つの篇のこと。
これらの文章は、斉で管仲の思想や、その後の黄老思想と呼ばれるものを研究した宗妍とその一門によるものと考えられています。
今回は以前、この「安心感の研究」で紹介した内容に相当する部分を、拙著「菅子四篇」から引用して掲載します。
次回以降は、その後の部分を続けて記事にしていく予定です。
心術上第三十六(短語十)
原文
心之在體、君之位也。九竅之有職、官之分也。心處其道、九竅循理。嗜欲充盈、目不見色、耳不聞聲。故曰上離其道、下失其事。毋代馬走。使盡其力。毋代鳥飛。使獘其翼。毋先物動。以観其則。動則失位、静乃自得。
書き下し文
心の體にあるは、君の位なり。九竅の職あるは、官の分なり。心その道におれば、九竅理にしたがう。嗜欲充盈せば、目、色を見ず、耳、聲を聞かず。故に曰く、上その道を離れれば、下その事を失う。馬に代って走るなかれ。その力を尽くさせよ。鳥に代って飛ぶなかれ。その翼を疲れさせよ。物に先立って動くことなかれ。以てその則を見よ。動けば則ちその位を失い、静かなれば乃ち自ら得
現代語訳
心は身体の中にあり、身体を治める役割を担っている。それは君主が国を治めているようなものだ。身体にある目や耳、鼻の穴など外に向かって開いている九つの穴にはそれぞれの役割がある。それは官吏がそれぞれの職分を守っているようなものだ。心が道に従うあり方をしていれば、九つの穴はその本来の理に従って正しく働く。見たい、聞きたい、という欲望が心に満ち溢れたならば、目は物事をあるがままに見ず、耳は言葉をそのままには聞かなくなってしまう。だから、治める役割を担ったものが、あるべきあり方をしていなければ、それに治められているものも、それぞれの役割を果たせなくなってしまうのだ。馬の代わりに走るようなことをするな。馬には馬の力を出し尽くさせるのだ。鳥に代って飛ぼうとするな。鳥にはその羽の力を出し尽くさせるのだ。外の出来事に先立って動こうとするな。出来事の起こり方、法則を見よ。動けばあるべき位置を失うが、静止していれば、その道にいて、その法則に従うことを自ずと叶えることができるのだ。
「菅子四篇」暖淡堂書房より
<簡単な解説>
「心術上」の冒頭で、心術という文章における重要な定義をしています。
国の君主というのは、身体における心と同じだ、といいます。
それを基点として、身体の器官が役所で働く役人のように見立てたり、心身の不整合が国の乱れとなっていったりという議論になっていきます。
「九竅」というのは身体にある九つの穴のこと。
目二つ、耳二つ、鼻二つ、口一つ、これらに下半身にあるもの二つを合わせて九つ。
これらはそれぞれの役割を持っています。
もし目が音を聞こうとしたり、口で光を感じようとしたりすると、身体が混乱します。
それぞれの機能を働かせるのがいい。
馬や鳥の例えも出てきます。
人と違って、馬は力強く、駆けることができます。
もし、人が馬に代わって長距離を駆けたりすると、どこかで疲れ切って倒れてしまいます。
鳥は羽根で空を飛べますが、そもそも人は飛べません。
無理に飛ぼうとすると、落下して死んでしまいます。
馬や鳥は、それぞれ得意なことが人よりもはるかに上手にできるのです。
それぞれに力を発揮してもらうのがよい。
この馬や鳥は、「宰相」、「将軍」、「官吏」達の例えでしょう。
君主はこれらの者達の能力を発揮させるべきであり、けっして代わりに自分が手を出すべきではないと言っているのです。
このように、それぞれの能力を十分に発揮することを初めの部分で説明します。
ここで忘れてはいけないのが、冒頭の「君主=心」という定義。
この定義をめぐって、この後の文章は続けられます。
菅子四篇 心術上 (1) 菅子四篇の紹介を再開します
春秋戦国時代にはたくさんの思想家が現れています。
その一派の文章を「管子」という書物にまとめているともいえます。
ただ、「論語」や「老子」、「孫子」、「韓非子」などに比べて読まれる機会は少ないようです。
その理由の一つは、手に取りやすい「管子」の書物が、日本ではあまり出版されていないことかと思います。
暖淡堂書房では皆さんの手に取りやすい電子書籍の形で「管子」関連書籍を販売しています。
「菅子四篇」はアマゾンのペーパーバックとしても入手可能です。
東洋思想の源流を概観するのにも効果的な書物になっています。
仏教が中国に受容され、その後禅として発展したことの背景も理解できるかもしれません。
ぜひご一読を。
またお立ち寄りください。
どうぞご贔屓に。

にほんブログ村ランキングに参加しています



